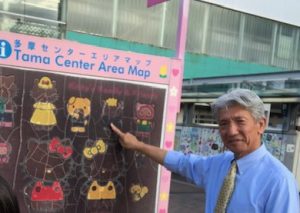街の歴史を物語っているのかもしれませんが、この全面錆びだらけの看板は誰がいつ何の目的で設置したものでしょうか。こうしたものにも気を配り、対応できる余裕…欲しいですね。
決算審査3日目が終わりました。最近は、個々個別の事業に対して質疑する人が少なくなったのかしら?‥‥まだ3日目にも関わらず、すでに教育費の質疑に入っています。昔?と比較をすると…というのも変ですが、教育費の質疑に入るのは5日目という時もありました。「職員の残業時間を減らす」ということが意識されたり、新型コロナ禍でなるべく短時間で効率よく…みたいなスタイルが定着したからかもしれませんが、「どこが違うんだろう」と思うのは、議員の発言持ち時間は過去も今も「30分」で変更しているわけではありません。
今日は最後の方で伊地智さんが「小中学校の配膳室」のことに触れ、給食センターから各小中学校に配送される給食を配膳する皆さんが働いている現場にエアコンが設置されていないことを指摘し、改善を求めておられました。猛暑が言われるようになり、ようやく小中学校にもエアコンが設置されるようになりましたが、でも全部の教室というわけにはいかず、「日常的に使用する部屋」が優先で、使用頻度の低い教室などにはエアコン設置がされていないのが現状です。。もちろん、配膳室にもエアコンはありません。現在は、扇風機で凌いでいるということですが、配膳室は衛生面のこともあり、扉などを開放することもできず密室状態になっており、とても過酷であると。私も今さらながら…ですが、「ホントだ!」とハッとしました。
既にその状態について、教育委員会も把握はしているようでしたが、予算的には余裕がなく、後回しというのか、対応ができていない状況だったようです。伊地智さんが働いている方々の「いのちに関わる問題」と指摘されており、配膳員の労働時間そのものが長くはないとしても、改善が必要だと訴えておられましたが、その通りと思った次第。学校給食センターから運ばれる給食やら食器やらの積み下ろしなどなど…肉体労働とも言え、エアコンの無い密室で仕事をせざるを得ないともなると…その状態が目に浮かぶようです。ちなみに、冬もストーブ1つしかないなかで仕事をされていて、それはそれは寒いんだそう。想像に難くないです。
と言っても、先立つ予算をどう確保するかが問題で、「エアコン設置すべき」と主張する側にとっても、「どこかを削らなければ」とつねに背中合わせ。ここもまた、「お金の使い方」という点では、考えておかなければならないところとも言えます。
それにしても、気候変動で、これまで経験したことのない酷暑が続いたりして‥‥そしてエアコンを入れずにはいられないような状況や状態…脱炭素でCO2 削減を考えるにせよ、省エネ節電には限界があります。「これからは学校の断熱化が求められる」という声もありましたが、私も同感。竹内昌義先生をお招きして、児童生徒が参加するワークショップでもやってみたいですね。

さて、公園管理について話題に上っていましたが、「雑草の繁茂」については、この時期は特に市民の方が気にされることですね。私も改めて、この夏は雑草の強さを身に沁みて感じましたが、やっぱり凄い生命力だなあとある意味関心。生育状況が良好すぎて、草刈りが追い付いていない市内の状況をあちこちで目の当たりにしています。
「多摩市って、みどりが多いとか言ってるけど、歩いたらジャングルだよね!」
と大笑いされたことを思い出します。決してその状態を放置したいわけではありません。本当は適切な管理をしたい。歩行空間に影響を及ぼすような場合には、苦情を伝えると早めの対応をしてくれるのですが、それにしても優先順位があるのは仕方がないこと。後回しにするわけでなくとも、限られた税金のなかで順番に対応されていくわけで、市民の方からの苦情があっても即対応ができないことも多いです。
しかし…こまったことに、そうして放置されていく雑草たちはますます勢いを増して、その生命力を発揮するという悪循環。私は雑草は花粉アレルギーの要因をつくりだしていると思っていますし、やぶ蚊、ダニ、ゴキブリなど虫発生、今日は蛇が住んでいた…という話しもありましたが、大げさに言えば、私たちの暮らしや健康に被害をもたらす存在になっていることを意識してほしいと感じています。


ということで、日常的な公園のお手入れというか、メンテナンス作業もしやすくすることが求められるのですが、私はそのチャンスの一つに「公園の大規模改修」があると思っています。改修を機に、育ち過ぎた樹木を伐採するとか、低木が低木ではない状態になっていることも多いので、いい感じの大きさにまで小さくするとか…あとは樹木などが密集しすぎているところもあるので、思いっきり伐採するとか、間引きするとか‥‥そうした対応をもっと意識して進めてほしいと考えています。ちょうど、近所の諏訪北公園も大規模改修が行われているのですが、「枯れたままの松がそのまま放置されてしまいそう」で、近所の方からも「あれはどうなるの?」とも心配の声があがっていました。そして、私の散歩コースでもあり、法面などの低木などがまるで放置されていて、何の手入れがなされないままになっているために、街路樹と一体化しそうになっている場所もあり‥‥「まさか、大規模改修工事が終わってもこのまま?」という懸念が。
あえて、そのことに触れて、質疑しておきましたが、「大規模改修中なので、日常の維持管理をストップしておりまして…」ということでした。なので、雑草そのまま、樹木、植栽などの剪定もされずで今夏は伸び放題だったということのようです。そしてまた、枯れ木の松も…工事を始めた時には枯れていなかったので、そのままだったと‥‥(公園のパトロールをすれば、目に入ると思うのだけれど…)。


とにかく、大規模改修工事が終わって、せっかく公園がリニューアルされて、心地よくなったにもかかわらず、「あれ?」になりませんように。そしてまた、これから次々と公園の大規模改修が行われるときにも、将来にわたっても日常管理の負担が軽減されるように対応してもらえるといいなと考えています。ちょうど、公園管理のことについては、これまでの「公園町寿命化計画」をつないだ次のバージョン「パークマネジメント計画」の策定が進んでいるのですが、その中でも今後の方向性が示されることになっていて、老朽化したトイレ改修をどうしていくか、老木になっている木々をどうするか、植栽をどうするかについても一定の指針が打ち出されるようなので期待しています。
いずれにせよ、「税金」をどうつかっていくのかが問題。私は「魅力あるまち」というのは、もちろん、イベントがにぎやかに行われることも大事ですし、お楽しみの催しがあることも時には必要だと思っていますが、それ以上に、ここで暮らす市民の日々を大切にできること、ていねいな暮らしを紡いでいけるような佇まいに価値をおけるようなまちづくりが大切ではないかと考えています。
多摩市の魅力は「みどり」であることは間違いなし。だからこそ、「みどり」の維持管理にはこだわり、景観も含めて、「いいなあ、このまち」と思われるようにしていきたいものです。